【主観で解説】文部科学省が「生成AIの暫定的ガイドライン」を公表【生成AI/ChatGPT】
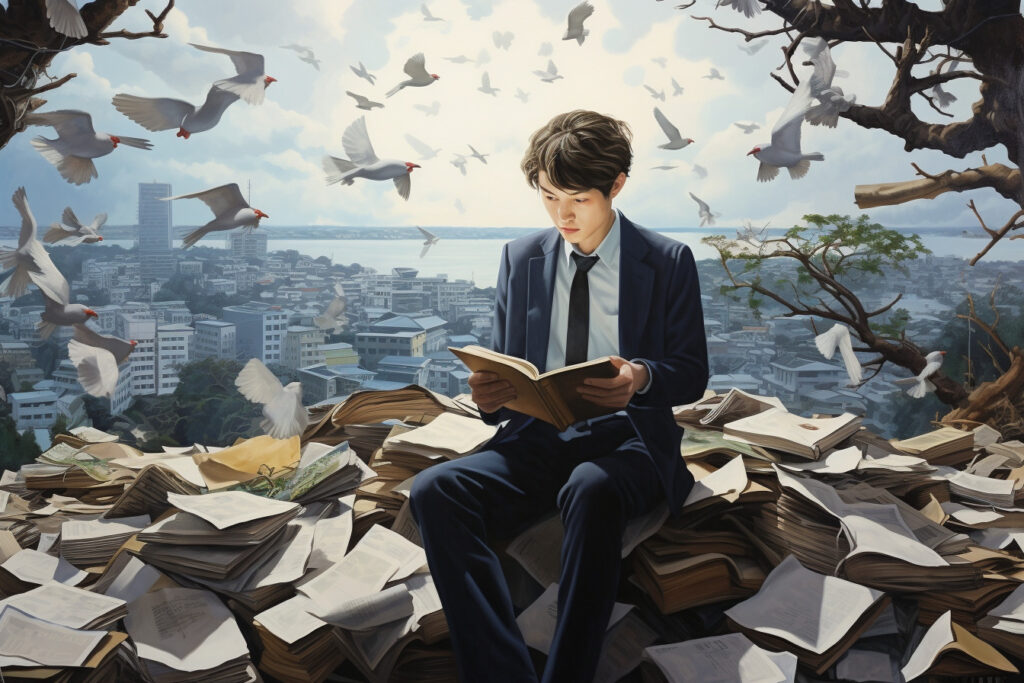
2023年7月、文部科学省より、「生成AIの暫定的なガイドライン」が公表されました!
自分の感想をふまえつつ、整理してみます。
(令和5年7月4日)初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン
https://www.mext.go.jp/content/20230710-mxt_shuukyo02-000030823_003.pdf
第一印象は、ちょっと残念!
ガイドラインを読んだ私の第一印象は、
「う~ん、ちょっと残念!」
というのが本音でした。
なぜなら、このガイドラインは「暫定的な」ものであり、「未来」に対するガイドラインとは言えないからです。
生成AIやChatGPTのような技術が急激に普及する中で、このガイドラインは少し後手に回っている印象を受けました。
しかし、中身には参考になる部分も多いので、一緒に見ていきましょう。
基本的な考え方
ガイドラインの中で示されている「AIに対する基本的な考え方」は以下の通りです。
- AI活用姿勢を育成することが重要
- 発達段階に応じたルールが必要
- 教育目的を達成するためのAIの使い方を心掛ける
- 教師のリテラシーも大切
要するに、「注意しながら、まずは限定的に使ってみよう」というのが文部科学省の基本的な姿勢のようです。
NGな使用例
ガイドラインでは、以下のようなAIの使用が推奨されていません。
- 安易な使用
- テストでの使用
- コンクールなどの作品提出
推奨される使用例
一方で、以下のような使用例が推奨されています。
- AIについて学ぶための使用
- AIの限界や活用についての議論
- アイデア出し
- 論点の整理
- 英会話の練習
上記のような事例が描かれていますが、ガイドラインだけはどうも分かりにくく、現場に丸投げな印象を受けました。
どうする?読書感想文の宿題
さて、本ガイドラインでとても参考になったのが、「読書感想文の宿題をどうするか?」という点です。
ガイドラインによると、読書感想⽂や⽇記、レポート等を課題として提出させるときは、
「単に提出させるのはダメ」
だそうです。
そうではなく、
「学習活動や自身の体験を記載する」
「口頭発表の場を設ける」
などの対策が提案されていました。
読書感想文やレポートに対するこの対策は、教育機関にとっては参考になるんじゃないかと思います。
学校運営側の視点
ガイドラインは主に「子どもがどう使うか」という視点で書かれていますが、教師や学校運営側の視点も重要です。
AIを使った働き方改革の期待や、個人情報の取り扱い、著作権侵害に関する注意点などが記載されています。
要は、民間企業と同じように、AIの力で働き方を変える取り組みが求められるということですね。
まとめ
本記事では、文科省から出た生成AIに対する教育現場でのガイドラインについて考察してみました。
教育現場での活用を今後も考えていきましょう。


