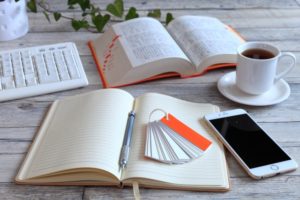高校生の進路選択NG集!こんな進路選択はダメだ!

高校生にとって進路選択は一大イベント!進路を決めるのって大変ですよね。
そこで、本記事では進路選択のNG集を紹介していきます。
進路選択NG6選
- NG例①:見学せずに決める
- NG例②:学部学科を決めずに、大学名で決める
- NG例③:受かりやすさで決める
- NG例④:セールストークに騙される
- NG例⑤:先生のオススメで決める
- NG例⑥:親の意見で決める
NG例①:見学せずに決める

学校見学ってめんどくさいなぁ。第一志望だけ行けばいいか~。
こういう高校生、とても多いです…
が、高校生の皆さんに強く言いたいことがあります!
それは「百聞は一見に如かず」ということ!可能性のある進路先は必ず足を運んで見学することをオススメします!できることなら、実際に学びや仕事の内容を聞いたり、体験できるともっと良いです。
大学や専門学校なら「オープンキャンパス」や「学校説明会」があります。就職の場合なら「会社見学」や「会社説明会」などの機会を利用しましょう。
「説明会の日程が合わない!」「説明会やってない!」なんて場合は、自分で問い合わせてどんどん行っちゃいましょう!企業も大学も、「入りたい」と言って来てくれる高校生を基本的には嫌がりませんよ♪
中には複数の大学や専門学校を受ける人もいると思いますが、基本的に行く可能性のある進路先にはすべて訪問しておくことが理想です。この手間は惜しんではいけません。
また、今はインターネットで情報を得ることができますが、やはり実際に行って得た情報の濃さには敵いません。見学をした高校生達の声を挙げてみます。
高校生の声
- 思っていたより、学びの内容や雰囲気が良かった!(悪かった)
- 想像以上に都会だった!(田舎だった)
- 場所が遠すぎて、通学できる自信がなくなった
- 男ばかり(女ばかり)で息苦しかった
などなど、挙げればキリがないですね。実際に入ってから「こんなはずじゃなかったのに!」と嘆くことがないように、できるだけ自分の目で見るようにしましょう。
「化学」が好きだった筆者も、高校2年生の頃に実際に「薬学部」のオープンキャンパスに行きました。「化学好き=薬学部」という安直な考えだったのですが、実際に待ち構えていたのは
実験用マウスの解剖・薬物投与・・・そして部屋には大量の生き物の臓器が!!!
もうギャー!!!って感じでした(笑) 情けない話ですが当時の僕には耐えられませんでした(笑)
でも、そのオープンキャンパスで実際の現場を体験したことで、自分の中から薬学という選択肢が消えたわけです。今思うと良い経験でした。
見学は必ず行きましょう!
NG例②:学部学科を決めずに、大学名で決める

行くなら有名な〇田大学か〇治大学でしょ!学部は・・・どこでもいいや!
これはかなりやってはいけない進路選択ですね。進学先選びは、「①学部・学科(専門性)を決めて、次に②大学を決める」のが大前提です。
なぜなら、A大学の経済学部に行くのと、B大学の経済学部の行くのでは、学びの内容にそこまで大きな差はないからです。一方で、同じ大学でも経済学部と法学部では、学びの内容も目指す進路も全く異なってきますよね。
志望校を選ぶ際は、大学の知名度やブランド名などに気を取られるのは避け、自分の学びたい分野へ進むことをまずは考えましょう。
NG例③:受かりやすさで決める(少し注意!)

本当は△△大学に行きたいけど、指定校推薦で確実に行ける〇〇大学にしよう!
「指定校推薦」とは、ざっくり言うと「出願すればほぼ受かる」入試方法です。
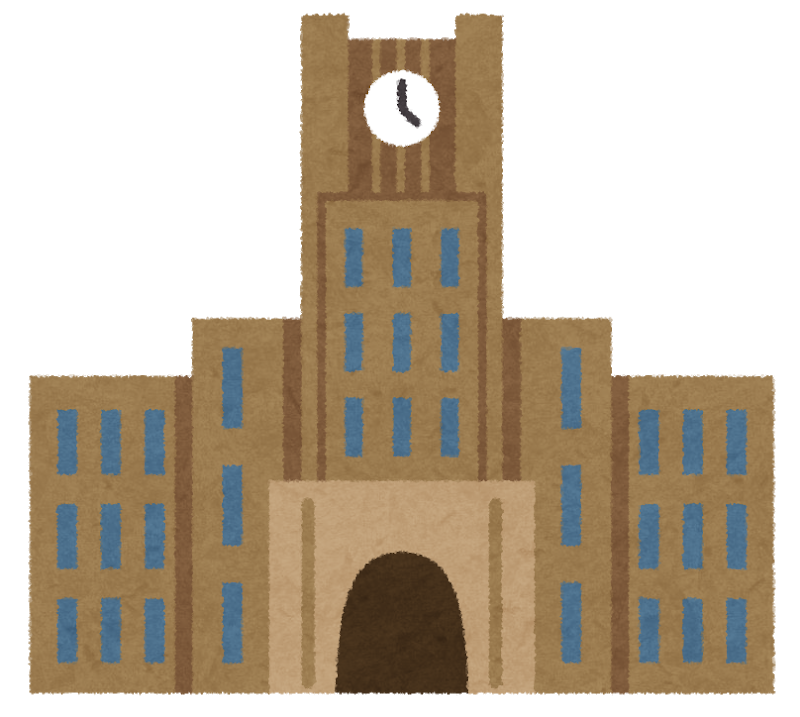
××高校に指定校推薦を送るよ!こっちも学生が欲しいから、受験生を送ってね!あ、試験はほぼ100%受かるから大丈夫!
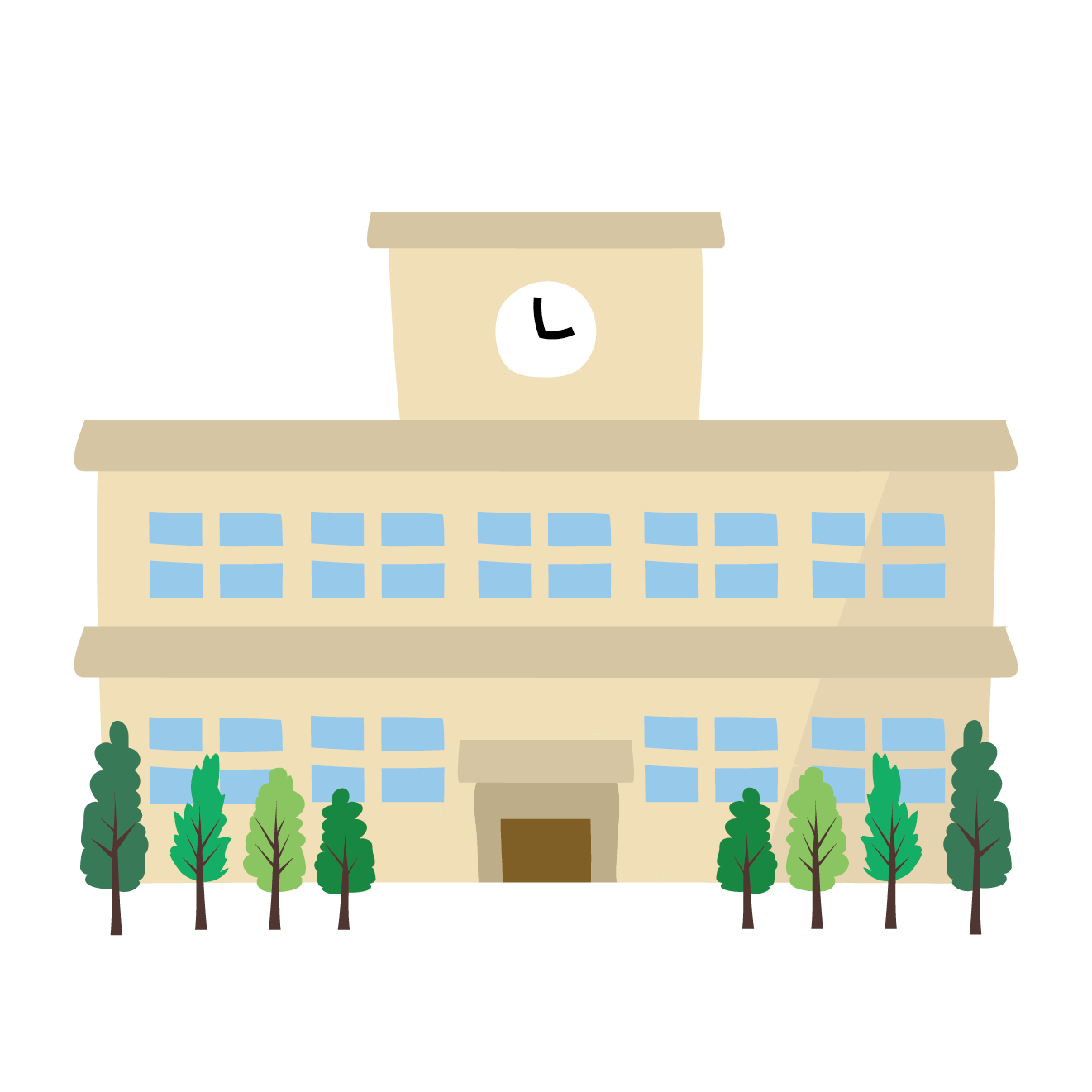
ありがたい!これで〇〇大学に確実に1人受かるぞ!
こんな感じで、大学側にも高校側にもメリットがあります。当然、受験生にとっても確実に受かる入試ということで安心感が違いますね。
ここで、「受かるかどうか分からない第一志望のA大学」と「指定校推薦で確実に合格できるB大学」があったとします。この状況でどうなるか、もう予想がつきますよね?
そうです。リスクを負ってA大学に挑戦するよりも、確実に受かるB大学へ進学する。こんな選択をする高校生がたくさんいるんです。見方によれば賢い選択ともいえますが、本当にそれでよいのでしょうか?
高校教師だった私の経験からすると、楽な方に流れて自分の進路を見失う生徒がとても多かったと感じています。
挑戦し、覚悟を持って自分の進路に向かった人は、自分の進路に対する意識が違います。また、楽な方に流れた場合、あとの後悔も大きくなるでしょう。
NG例④:セールストークに騙される

そこの君!うちの大学なら楽しいキャンパスライフが送れるよ!就職率だっていいし、困った時はいろんなサポートがあるよ!君ならうちに絶対合ってるよ!
こんなセールストークにあったことありませんか?当然ですが、大学だって企業だって基本的には商売です。「学校説明会」や「会社説明会」は、とにかく良いことをアピールして伝えるものですよね。
この少子化・人手不足の今の時代、大学や企業にとって、入学生や新入社員の獲得はめちゃめちゃ大変なんです!
実際に私も大学職員として高校生に説明会を実施していますが、とにかく良いことを伝えまくります。こんな感じで(笑)

そこの君!うちの大学なら楽しいキャンパスライフが送れるよ!(自分次第だけど) 就職率だっていいし(数字をごまかしてるから)、 困った時はいろんなサポートがあるよ!(実際はほとんど放置だけど) 君ならうちに絶対合ってるよ!(まぁみんなに言ってるけどね)
↑この例はちょっと極端でしたね(笑)
しかし、基本的には大学や会社も、自分たちの悪いことを言うわけがないんです。甘いセールストークには騙されないようにしましょう!
NG例⑤:先生のオススメで決める
高校生の進路決定において絶大な影響力を持っているのが高校の先生方。普通に考えると先生なら信頼できる!と思いそうですが、実は先生のアドバイスは要注意。
中にはとても熱心で情熱的で、真剣に皆さんの進路について考えてくれるような素晴らしい先生もたくさんいるでしょう。ですが、先生のアドバイスが必ずしも有効ではない場合もあります。以下の3点において注意が必要です。
先生と生徒が多重関係にある
先生のアドバイスが危険な最大の理由が、多重関係に当たるということです。
「多重関係」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?これは、人と人との関わりの中に、複数の関係性があるということです。多重関係にある人の支援は、様々な感情が働き、うまくいかないものです。
先生の進路のアドバイスに注意が必要な理由に、「①教える人(教師)と教わる人(生徒)」という関係に「②進路についてアドバイスする人とされる人」という新しい関係があるためです。やはり、立場や感情をゼロにして考えることは難しいでしょう。
先生にも大人の事情がある
多重関係の悪い例。「先生にも大人の事情がある」という例がこれです。
どういうことかと言うと、学校にも「○○大学何名合格!」みたいな実績が必要なんです。そのため、進路を担当する先生は合格実績を出さないといけないプレッシャーがあったりします。
実績を出すために、先生は生徒の希望と違う受験先を勧める場合があります。綺麗事を抜きで言えば、少子化の進む今の教育業界は激戦です。実績なしには生き残れません。これは元高校教師・大学職員として働いている私がたくさん見てきたことなので、実際にたくさんあります。
先生が勧める進路先に疑問を持ったら、そこはしっかりと疑うようにしましょう。
民間企業で働いた経験がない
3つ目がこれ。学校の先生は、いわゆる民間企業で働いた経験がない人がほとんどです。
また、もともと真面目で勉強が得意な人が多いです。
ですので、キャリア支援というと、どうしても偏った意見になりがちです。その点はよく理解して、先生のアドバイスを受けるようにしましょう。(これは先生が悪いわけではありません。先生には先生の役割があるということです)
NG例⑥:親の意見で決める
最後のNG例が、親の意見のままに決めてしまうこと。筆者はいろんな高校生を見て来ましたが、これが一番厄介で難しいことかもしれません。
多くの親は、子供のためを思っていろいろなアドバイスを言ってくれるでしょう。18歳の高校生といえば、まだ社会で働いた経験もありませんし、経済的にも自立していません。親の意見は無視できるものではありません。
ですが、これも多重関係です。感情や利害関係が入りまくる親子の関係で、冷静な進路選択ができるとは限りません。中には、自分のためというよりも親や家族のために進路を選ぶ場合もあるでしょう。仕方がない部分もあるかもしれません。
ですが、親といえど他人です。18を迎えた高校生なら、精神的にも物理的にも親離れをする年齢です。親はあなたに代わってあなたの人生を生きてくれるわけではありません。自分の人生は自分で生きていかないといけないのです。
ですので、やはり自分の進路は自分で選択していく必要があります。親の意見もほどほどに。
結論:自分の人生は自分で決めよう!
ここまで6つのNG例を紹介してきましたが、いかがでしょうか?
大切なのは、自分の進路は自分の意志で決めることです。
他の誰でもない、自分だけの人生ですから、最終的に責任を持てるのは自分だけです。あとで誰かを責めるのだけはやってはいけません。
進路選択NG6選
- NG例①:見学せずに決める
- NG例②:学部学科を決めずに、大学名で決める
- NG例③:受かりやすさで決める
- NG例④:セールストークに騙される
- NG例⑤:先生のオススメで決める
- NG例⑥:親の意見で決める
以上、こんな進路選択NG集!でした!